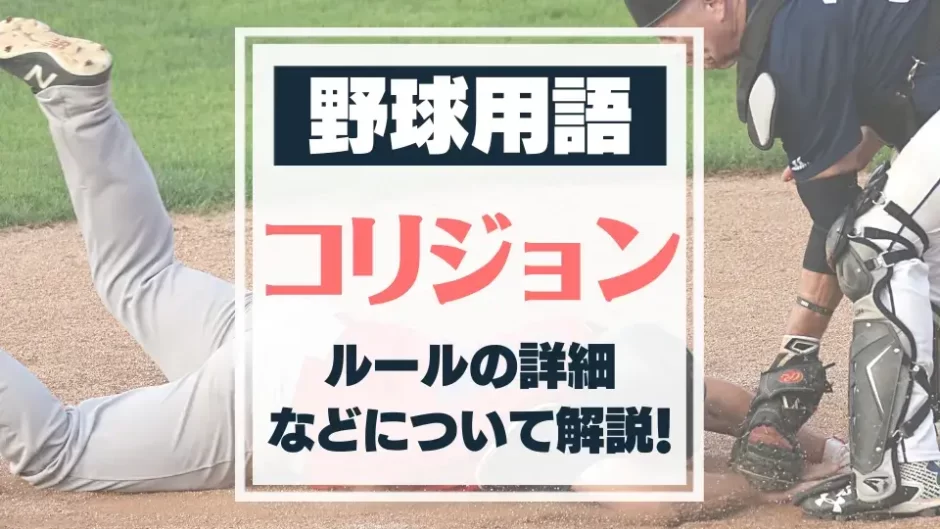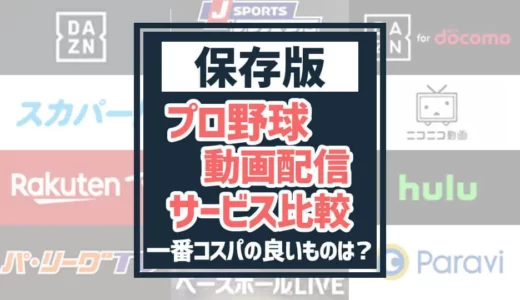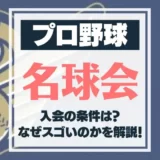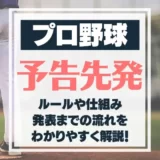この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
球春到来!いよいよ2025年シーズンがスタート!!!
コスパ重視のあなたには「DAZN」!
12球団試合を見たいのあなたには「スカパー」!
推し球団がパ・リーグのあなたには「パ・リーグTV」!
| サービス |  DAZN |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |  ファイターズMIRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) | 1球団 (日ハム) |
| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |
| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 | 2,500円 |
| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
おすすめNo.1はコチラ
「コリジョンルールってよく聞くけど、どんなルール?」
「コリジョンルールが導入されたきっかけやメリット・デメリットが知りたい」
このような疑問や考えを持っている人はいるのではないでしょうか。
コリジョンルールは2016年に導入された制度ですが、詳しい内容を知らない人多いのではないでしょうか!
今回この記事では「コリジョン」の意味から、どんなルールなのか?、導入のメリット・デメリットまで、小学生でもわかるように解説していきます!
この記事はで読むことができます。
まずは簡単に、用語解説からいきます!
用語解説
- コリジョンとは?
- 本塁での走者と捕手の衝突を避けるために設けられたルールのこと。
正式名称と導入目的
コリジョンの正式名称は、「コリジョンルール」と言われています。
一番の目的は、ホームベース付近での捕手と走者が衝突してケガが発生するのを防ぐことです。
MLBでは2014年から、日本プロ野球では2016年からルールが導入されました。
公認野球規則には、6.01(i)「本塁での衝突プレー」にコリジョンルールについてが記されています。
 バント店長
バント店長

コリジョンルールは主に走者と捕手に関するルールです。
本塁上での衝突防止の観点から、詳細なルールが設けられていますので、走者・捕手それぞれのルール内容を紹介します。
まずは、コリジョンルールの走者に関する部分です。
本塁に向かっている走者が本塁のカバーをする野手に対して、意図的に接触しようとした場合、審判は走者にアウトを宣告します。
野手がボールを持っているかどうかに関わらず、このルールは適用されます。
このケースの場合ボールデットとなり、他の走者は接触が起きた時点で最後に触れていた塁に戻らなければなりません。
一方、捕手の場合を見ていきます。
捕手がボールを持っていない状態で、本塁に向かってきている走者をブロックすることは禁止されています。
ボールを持たないまま走者が走っている場所を妨害したと審判が判断した場合、走者はセーフとなり得点が認められます。
捕手が送球を受け取る際に走者が走っているエリアをふさぐ形になった場合は、コリジョンルールは適用されません。
また走者がスライディングをして捕手との接触を回避できた場合も、捕手に対してコリジョンルールの適用外となります。
以上が走者と捕手のコリジョンルールの内容となります。
ポイントは、走者・捕手ともに意図的に妨害をするかどうかが、コリジョンルール適用の分かれ目でしょう。
走者はできるだけスライディングをして接触を避け、捕手は走路に立たないようプレー中の立ち位置に注意が必要です。

現在では当たり前のように運用されているコリジョンルールですが、導入されたのはわずか数年前のことです。
ここでは、MLBとプロ野球それぞれのコリジョンルール導入のきっかけについて解説します。
どのような経緯で導入されたのか、ぜひ参考にしてください。
メジャーリーグ(MLB)
コリジョンルールが生まれたのは、MLBでのある出来事が発端でした。
フロリダ・マーリンズ 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ
ジャイアンツのバスター・ポージー選手は、本塁でのクロスプレイの際に、ランナーのスコット・カズンズ選手から激しいタックルを受けました。
このプレーで、バスター・ポージー選手は、左下腿の腓骨骨折と左足首靱帯断裂の重傷を負ってしまうことに。
シーズン中の復帰は絶望的になってしまいました。
ポージー選手が負傷する前にも接触プレーでの負傷が続いていたことから、本塁上でのクロスプレーに関する議論が更に進んでいくことになりました。
このプレーがきっかけとなり、MLBは2014年に本塁上での接触プレーを禁止事項に設けました。
 バント店長
バント店長
日本プロ野球
日本のプロ野球でコリジョンルールが導入されたのは、MLBでの導入から2年後の2016年でした。
日本プロ野球でも、MLB同様に導入以前から本塁での接触プレーについて問題視する声がありました。
その事例のひとつが、元阪神タイガースのマートン選手の捕手に対するタックルプレーです。
マートン選手のタックルでケガをする選手も出ていたことから、コリジョンルールの制定が加速しました。
2015年の「みやざきフェニックス・リーグ」で最初に試験運用。
その後、2016年から正式導入が決まり、現在に至ります。
 バント店長
バント店長
ここではコリジョンルールのメリットとデメリットについて解説していきます!
接触プレーが減り負傷する選手が減った
コリジョンルールの導入で一番のメリットは、ケガのリスクが減ったことでしょう。
接触プレーを回避するために厳格なルールが適用されたことから、タックルプレーがなくなり、意図的な接触プレーが減りました。
接触プレーによるケガも減っているので、ルールの導入が良い方向へ向かっていますね。
妨害されるリスクの減少で、積極的に本塁を狙える
コリジョンルールの適用前よりも、積極的に本塁へ突入する走者が増えています。
実際の試合では、シングルヒットで2塁から本塁へ向かうケースが当たり前になっている印象を受けますね。
走者が本塁へ向かうことが増えたので、野手は本塁への正確な送球が求められるようになりました。
1点を争う展開ではより送球の重要性が増してきています。
審判の裁量で試合に影響が出る
コリジョンルールが適用されるかは審判の一存で決まります。
選手側はコリジョンではないと思っても、審判がコリジョンと判断した場合、試合展開に大きな影響を及ぼすこともあります。
2019年からはコリジョンもリクエスト制度の対象となったため、ビデオ判定を用いて判断できるようになりました。
コリジョンルールが導入されてから、実際の試合では何度もルールが適用される場面がありました。
ここでは実際にルールが適用された事例をもとに解説をします。どのような場面でルールが適用されたのか参考にしましょう。
事例①
こちらの事例は、センター前ヒットで本塁へ突入した2塁ランナーに対して、捕手が走路をふさいだことでコリジョンルールが成立。得点が認められました。
センターからの送球がそれたわけではなく、捕手があらかじめ走路にいました。
このことから、走者は走路を外れて走らなければいけない形となったのがルール適用の要因です。
事例②
2つ目の事例も、捕手が本塁をふさいでしまったケースです。
ファーストへの内野ゴロで一塁手は本塁へ送球。
その際に捕手は右足が本塁を踏んでいる状態となっており、走者が本塁を踏めないと判断されコリジョンが適用。
走者はセーフとなり1点が入りました。
一塁手からの送球を受ける際の位置としては、本塁の上が適していると思われます。
しかし、走路をふさがない立ち位置を把握する必要があるでしょう。
今回はコリジョンルールについての詳しいルール内容や、実際の事例をもとに解説をしました。
衝突を防ぐためにも、捕手の位置や走者が気をつけるべき部分が学べたのではないでしょうか。
コリジョンルールが適用されるか否かで、試合展開にも大きく影響されます。
プロ野球を観戦する人はルールを把握しておくと、プレーを深掘りしながら自分なりの見方を持つことで試合を楽しめるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
プロ野球中継サービス一覧全15サービス一覧
| サービス |  DAZN 期間限定無料! |  DMM×DAZN |  DAZN for docomo |  スカパー |  パ・リーグTV |  Jスポーツ |  ベースボールLIVE |  Rakuten TV |  フジテレビONEsmart |  ニコニコプロ野球チャンネル |  Hulu |  Paravi | ホークスTV |  虎テレ |  GIANTS TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象球団 | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 11球団 (広島除く) | 12球団 | 6球団 (パ・リーグ) | 5球団 (広島・横浜・中日・楽天・オリックス) | 6球団 (パ・リーグ) | 6球団 (パ・リーグ) | 2球団 (西武、ヤクルト) | 1球団 (横浜) | 1球団 (巨人) | 1球団 (横浜) | 6球団 (パ・リーグ) | 1球団 (阪神) | 1球団 (巨人) |
| 月額料金 (税込) | 2,300円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,483円 | 1,595円 | 1,980円 | 660円 | 702円 | 1,100円 | 550円 ※プレミアム会員 | 1,026円 | 1,017円 | 900円 | 660円 | 1,320円 |
| 1球団あたり の月額 | 209円 | 316円 | 382円 | 374円 | 266円 | 396円 | 110円 | 117円 | 550円 | 550円 | 1,026円 | 1,017円 | 150円 | 660円 | 1,320円 |
| ポイント | 野球配信でのコスパNo.1◎ 好みにあったプラン選択が可能 | DAZN通常契約よりお得 DMMサービスも楽しめる最強プラン | スポーツコンテンツ量がかなり豊富 docomoユーザーにおすすめ | 唯一12球団網羅 | 2012年以降のパ・リーグ主催試合がすべて見放題 2軍戦も視聴可能 | 広島戦メインでは最安 | ソフトバンクユーザーならさらにお得に パ・リーグメインならコスパ最強 | ダイジェスト版は無料で視聴可能 楽天ポイント使用可 | バラエティ等も合わせて視聴可能 | 基本視聴は無料 プレミアム会員で見逃し放送が視聴可能に | 日テレ系のドラマが豊富 無料トライアルあり | 横浜のドキュメンタリー作品も視聴可能 球団の裏側まで見たい人におすすめ | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 | 球団オリジナルコンテンツが豊富 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
迷った方はこちら